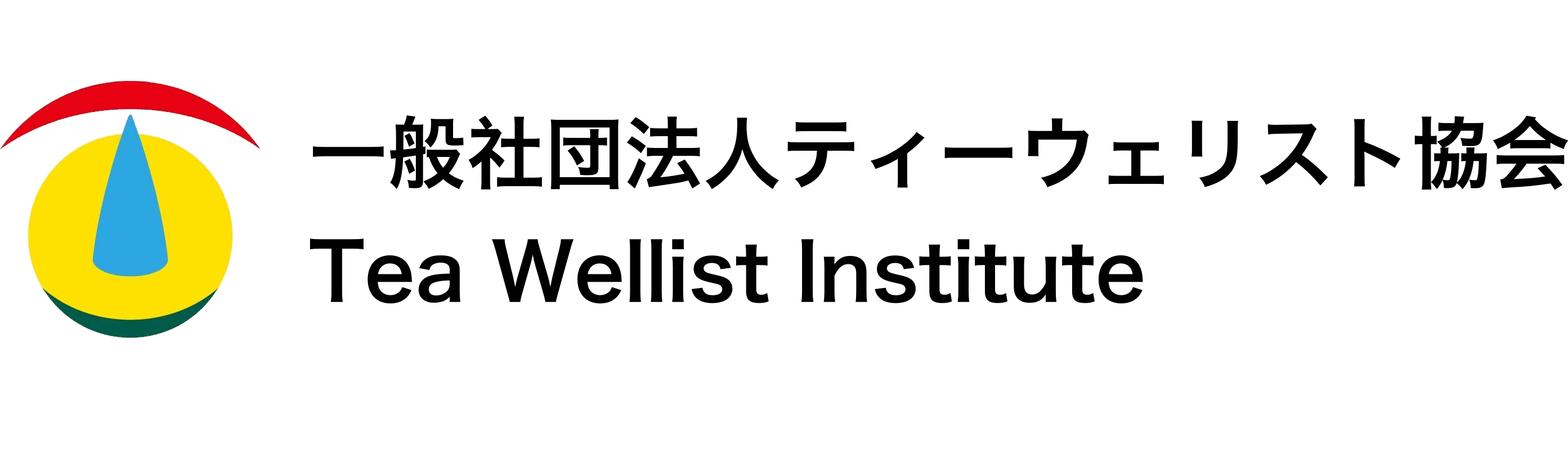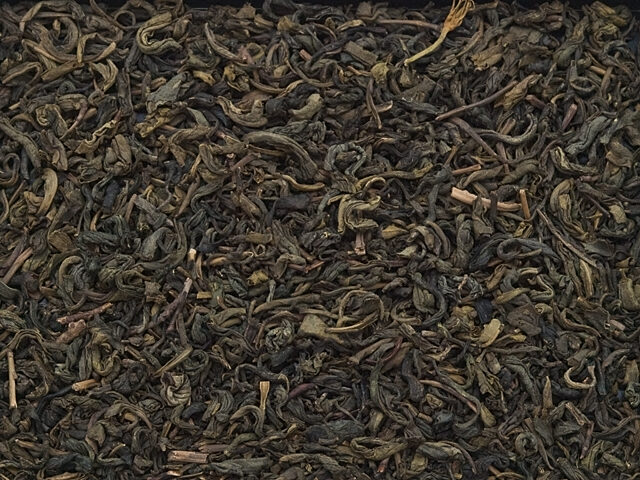来週のティーコンシェルジュ2級講座で、
世界のお茶の飲み方を試してみようと思います。
テキストに出来上がり予想図がほしかったので、
いくつか試作してみました。
まずは・・・
昔々お茶はいろいろなものを入れてスープのように飲んだり、
葉を漬物のようにして食べられていました。
(今も一部残っていますが。)
たぶん、なんだか元気になる葉っぱは、硬くて苦い。
なんとかして口に入れられるようにしよう。と料理されたのでは?
その飲み方のひとつ、擂茶(らいちゃ、れいちゃ)を作りました。
といっても、今手軽にできる方法で再現です。
ピーナツやゴマ、ハトムギなどと生の茶の葉をすりこぎですり、
お湯を入れて飲む(食べる?)方法です。
生の茶の葉はないので、粉末の緑茶を入れ、
お湯の代わりに煮出したウーロン茶を使いました。
これは、台湾の客家料理店でやっていた方法を真似しました。
擂ったのは、黒豆、松の実、白ゴマ、ハトムギ
そして、冬なのでゆずをすこし入れました。
今も中国で擂茶をつくるときは、
季節のものを入れて養生するそうです。
そして、砂糖!
甘くするととてもおいしくなります。
塩を入れるとスープにより近くなるそうです。
農作業や戦争時の簡易食がわりだったとか。
お茶にはだしのようなコクがありますよね。
簡易的な食事を「お茶の子」と昔から言うように、
お茶づけなど簡単にできる料理にお茶はよく使われてたんではないかな。
と思いました。
さて、次回の講座ではどんな味になるのでしょう(*^▽^*)
関連記事
ジャスミン茶の品質とグレードの違いについて
ジャスミン茶(茉莉花茶)は100種類以上もグレードがあるといわれるほどポピュラーな花茶です。しかしジャスミンの蕾で香りをつけた本物から香料などを添加しただけのものあり、品質の差やグレードがわかりずらいといわれるお茶のひとつですが、ここではティーウェリストがわかりやすく解説いたしております。
ティーウェリストが教える血液サラサラになるルチンが豊富に含まれている「まるごと韃靼蕎麦茶」
脳や心臓の疾患になりやすい厳寒期にはルチンが豊富な韃靼そば茶で身体づくりがおすすめ
ハーブティーやお茶、コーヒーのスペシャリスト、ティーウェリストが教える「血液サラサラになることで知られているポリフェノールの一種、ルチン豊富なまるごと韃靼蕎麦茶」のご案内。牛乳と混ぜるだけで手軽に飲める粉末韃靼蕎麦茶です。お子様から高齢者でもノンカフェインで有機栽培原料の韃靼蕎麦茶なので安心です。